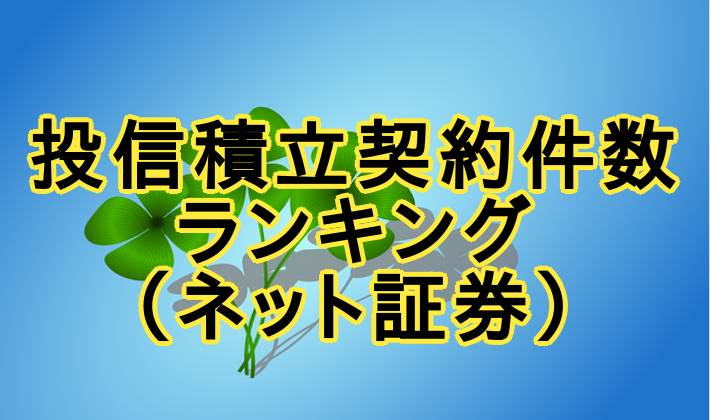投信の信託報酬は安いほど良いのですか?【A:信託報酬は低い方が良いです。】

モーニングスター公式サイトでこんな記事を見かけました。
投信の信託報酬は安いほど良いのですか? 最高の信託報酬年3.3%超から考える運用コストとの付き合い方🔗
詳細は、上の記事を確認していただきたいですが、「高い信託報酬には、高いなりの理由がある。それは絶対収益を目指しているから」とのことです。
この「絶対収益」とは、絶対的な収益という意味で、株式市場や債券市場などが上がっても下がっても、常にプラスの収益を確保することを目指しています。(もちろん、常に絶対収益になることを保証しません。)
我が家では、「信託報酬は安いほど良い」と考え、愚直に株式インデックス・ファンドの積立投資を2014年から継続しています。
今回は、我が家のような一般的な世帯の資産形成では、「信託報酬は安いほど良い」と考えている理由を解説しています。
この記事で分かること(信託報酬は安いほど良い理由)
- 信託報酬は安いほど、トータル・リターンが良い傾向になる。
- リスクを抑えた運用をしたければ、投資用資金の現金比率を高めることで対応可能。
最後までご覧いただき、資産運用のヒントにしていただければ幸いです。
信託報酬は安いほど良い理由1つ目

信託報酬は安いほど良いと考えている理由の1つ目は、「信託報酬は安いほど、トータル・リターンが良くなる傾向がある」からです。
具体的には次の記事を確認してください。↓
【つみたてNISA対象商品で検証】株式インデックス・ファンドは、実質コストが低いとトータルリターンが高い!?🔗
要約すると、株式インデックス・ファンドの場合「実質コストが低い株式インデックス・ファンドほど、直近のトータル・リターンが高くなる!」となります。
数十億円もの資産があるような富裕層であっても、一般的な世帯の資産形成であっても、買うべきリスク商品は「株式市場を広くカバーする低コストなインデックス・ファンド」であることは、ノーベル経済学賞を受賞した現代ポートフォリオ理論などからでも明らかです。
信託報酬は安いほど良い理由2つ目
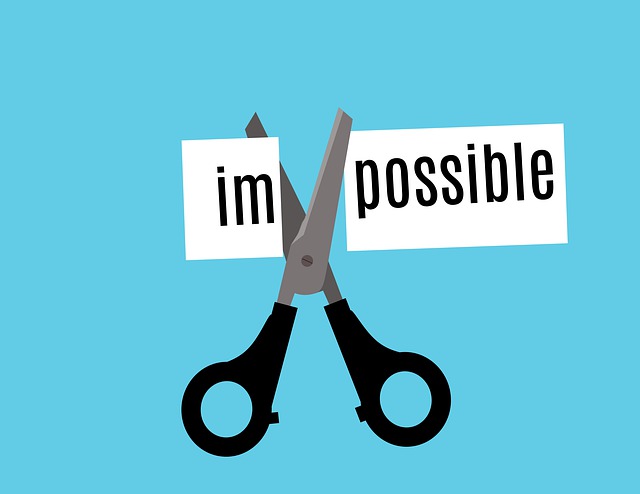
確かに、株式という資産クラスはハイリスクです。
初めの記事にもあるように、「リスクを抑えた運用」をしたい気も分かります。
しかし、「リスクを抑えた運用」をするために、わざわざ高コストな信託報酬を払う必要はありません。
「リスクを抑えた運用」を実現する方法は、安全資産である現金や個人向け国債の比率を高めることで実現可能です。
現代ポートフォリオでは、老若男女を問わず「株式市場を広くカバーしたインデックス・ファンド」を買うこと。
さらに、個人投資家がやるべきことは、たった一つ。どれだけ「インデックス・ファンド」を買うかを決めることです。
個人投資家がやるべきことは、たった一つ。
どれだけ「インデックス・ファンド」を買うかを決めること。
さらに踏み込んで言えば、「リスク資産を買わない金額(=現金比率)」を決めることです。
具体的には次の記事を確認してください。
【最大損失を計算】あなたのポートフォリオ(インデックス運用)のリスクを見積もる簡便方法(トービンの分離定理)
現金比率が決まれば、運用資産全体の「リスク、期待リターン」が決まります。
わざわざ高コストな信託報酬を払う必要はありません。
まとめ

今回は、個人の資産形成では、「信託報酬は安いほど良い」と考えている理由を解説しました。
「信託報酬は安いほど良い理由」
- 信託報酬は安いほど、トータル・リターンが良い傾向になる。
- リスクを抑えた運用をしたければ、投資用資金の現金比率を高めることで対応可能。
現代ポートフォリオでは、老若男女を問わず「株式市場を広くカバーしたインデックス・ファンド」を買うこと。
さらに、個人投資家がやるべきことは、たった一つ。どれだけ「インデックス・ファンド」を買うかを決めることです。
皆さんには、徹底的にコストを意識して、買うべき金融商品を選んでいただきたいと思います。
「長期・分散・低コスト」これが、どんな人でも資産形成を成功させるために必要な合言葉です。
関連記事です。
世界最大級の運用会社「バンガード社」が提唱している個人の資産運用のモデルポートフォリオです。ぜひ参考にしてください。
【資産形成】バンガード社ポートフォリオ配分モデルから資産配分・リスク分散を考える
退職後の生活費(老後資金)を準備するなら、国が法制度化した個人型確定拠出年金制度(iDeCo)を活用しましょう!
https://vegetables-asstes.com/2021-0814-ideco/4365/